清掃ロボットを“育てる”という発想

目次
- 導入当初、現場の空気は冷ややかだった
- ロボットは“人の代わり”ではなく“共に働くパートナー”
- ロボットに名前を付ける?――“愛着”が生まれた瞬間
- 定着の鍵は「心理的不安のケア」と「育てる意識の共有」
- まとめ:人とロボットの“協働”が次の清掃のカタチ
- スタッフの声:清掃ロボットと“協働”する日々
◆導入当初、現場の空気は冷ややかだった
ある商業施設で清掃ロボット「JINNY」のPOC(現場実証試験)をしたときのこと。現場スタッフの一人がこうつぶやきました。
「ロボットが来たら、私たちの仕事がなくなるんじゃないですか?」
これは決して珍しい反応ではありません。ロボットの導入に際して、多くの施設で似たような声があがります。現場でのロボット導入に対する「不安感」は、現場やロボットの仕様に関するモチベーションに大きく影響するため、管理側がしっかりと、スタッフ側の視点に立った説明をすることが大切です。
ですが、先に導入したある施設では、スタッフの間でJINNYにニックネームがつけられ、メンテナンス記録を丁寧に管理し、まるで共に働く同僚のように接するようになっていました。この変化の背景には、「ロボットを育てる」という意識の醸成がありました。

◆ロボットは“人の代わり”ではなく“共に働くパートナー”
清掃ロボットは、広い床面の清掃作業を効率化するツールとして導入されます。
しかし、現場での役割は単純な自動化に留まりません。
現場で実際にロボットを活用している企業では、スタッフが手作業で行っていた広範囲の清掃をロボットが担当することで、スタッフは棚や什器の拭き上げ、トイレ清掃、設備チェックなど、より専門的な作業に集中できるようになった、という声が多く聞かれます。
つまり「人にしかできない仕事に集中できる環境」を作ることで、現場の生産性と清掃品質がともに向上するのです。
◆ロボットに名前を付ける?――“愛着”が生まれた瞬間
導入後にロボットへ愛着が生まれる現場では、いくつか共通する傾向があります。
・名前をつける(例:「ひかりちゃん」「そうじ郎」など)
・清掃前に「今日も頼むね」と声をかける
・トラブルやエラー時に、原因を調べて改善しようとする姿勢が強まる
こうした“ケア”の感覚が定着していくことで、ロボットは単なる機械ではなく、現場の一員として認識されるようになります。その結果、使い方の習熟も早くなり、日常の運用も安定していきます。

◆定着の鍵は「心理的不安のケア」と「育てる意識の共有」
清掃ロボットの導入をスムーズに進めるには、現場スタッフの心理的不安を早い段階で軽減することが不可欠です。実際に導入支援を行う中で有効だった施策には、次のようなものがあります。
・ロボットと人の役割を「分担」する方針の明示
→ 人の業務が奪われるのではなく、再配置されることを説明する
・ロボットの運用を“育てるプロセス”として紹介
→ 最初はうまく走れないこともあるが、調整していく過程を前向きに捉える
・スタッフに「名づけ」や「運用ルール作り」への参加を促す
→ ロボットに主体的に関わる意識が芽生える
特に、「育てる感覚」を持つことが、現場の受容を大きく左右します。
◆まとめ:人とロボットの“協働”が次の清掃のカタチ
清掃現場の課題――人手不足、業務の属人化、清掃品質のばらつき――は、ロボットの導入だけでは根本的には解決できません。重要なのは、ロボットを「どのように現場に定着させるか」という視点。
人とロボットがそれぞれの得意分野を活かし、協働する体制を整えることで、職場全体の生産性や満足度が向上します。
ロボットを“育てる”という発想は、単なるツール導入から一歩進んだ、現場マネジメントの考え方です。その第一歩として、スタッフとの信頼関係づくりから始めてみてはいかがでしょうか。
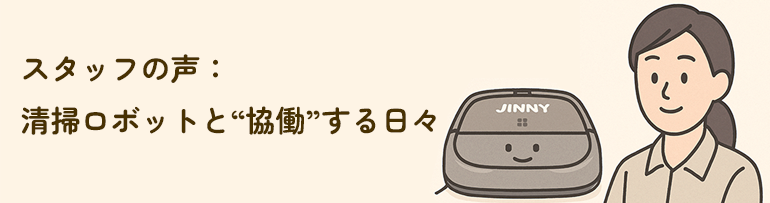
今回は、実際に清掃ロボット「JINNY」と一緒に働く現場スタッフの皆さんから寄せられた、リアルな声をご紹介します。導入のヒントや、現場のあたたかさが感じられるエピソードの数々を、ぜひご覧ください。
◆名前をつけた理由や由来を教えてください
ロボットに名前をつけるのは、自然な流れだったと思います。一緒に働く仲間には、やはり呼び名があった方がいいですしね。人間も、子どもが生まれてから名前を考えるのではなく、生まれる前からいろいろと候補を考えますよね。それと同じ感覚です。
導入当初は私が名付けていましたが、今では店舗ごとにクリーンスタッフが命名しています。その地域の名産品にちなんだ名前が多いようです。
また、導入前にスタッフに動画を見てもらっているので、実物が到着すると「やっと会えた!」「待ってたよ!」といった声があがります。まるで赤ちゃんの誕生を心待ちにするような感情が、自然と生まれているのかもしれませんね。
—
◆ロボットに声をかけることはありますか?
スタッフからの声がけは、日常的に行われています。ぬいぐるみに接するようにとまではいきませんが、「今日は、はなまるー」とか、業務が終わったときに労うような場面では、自然と言葉が出る感じです。動きが止まったときには「さぼってる?」「休まず働けー」といった、冗談交じりの叱咤激励が飛ぶこともあります(笑)。
JINNYに、清掃ルートやスケジュールを本当に相談することはありませんが、スタッフはよくひとり言のようにつぶやいています。例えば、売場レイアウトの変更があった日は、「今日はこっちやめて、あっちを先にしようか」とロボットに語りかけながら設定を変更したりしています。
導入当初は「どうせ聞こえてないし」と気楽に悪口を言ったりもしていたのですが、使っていくうちに「もしかして聞こえてるかも…」と感じるようになってきて。今では、気持ちよく働いてもらえるように、なるべく前向きな声がけを意識しているようです。
中には、「この人が操作するとすぐ働くけど、あの人だと時間がかかる」といった、“相性の話”が出ることもあります。
—
◆メンテナンスも、まるで“ケア”のように
JINNY20の上部にある突起部分を、私たちは「脳みそ」と呼んでいます。メンテナンスの際にはその“脳みそ”を床につけないよう、傷つかないように、必ず保護用“手”と呼んでおり、やさしく拭きながらゴミを取っています。
—
◆調子が悪い時は“心配”の声も
先日、メンテナンス担当の方(私たちは“みっちー先生”と呼んでいます)が、調子の悪いロボットを引き取りに来られました。
「体調が悪くなったら、お父さん(先生)が迎えに来てくれるんだね…」と、別れの挨拶も見送りもできず、スタッフも寂しがっていました。
また、休み明けに出勤してきたスタッフが「昨日、動いてた?」と気にかけたり、動かない時には「今日はお休みみたい」と話しかけながらラックに戻す場面もあります。調子が悪いときには「反抗期かな」「体調不良?」「職場放棄!?」と、それぞれにユニークな表現で受け止めています。JINNY20の前に使っていたロボットでは、仕事をしない“問題児”がいて、「札付き」とあだ名されていたこともありました(笑)。
また、清掃中に何かに引っかかって停止してしまったときには、「○○が止まってます!」と“救急要請”が発生。すぐに“ロボコップ”(管理担当者)がタブレットを持って駆けつけ、応急処置に当たります。
このように、ロボットとの日々のやりとりには、「愛着」と「共に働いているという実感」がたくさん詰まっています。
ロボットは単なる“道具”ではなく、現場の仲間として、大切にされている存在なのです。
