抵抗感? 現場はなぜ清掃ロボットを嫌がるのか?
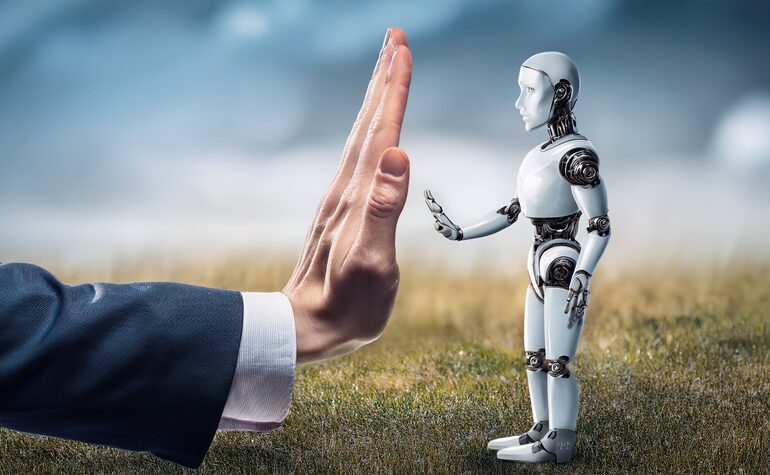
目次
はじめに
同じ会社に長く勤めていると、社内ルールの変更や新システムの導入の話がもちあがることがあります。経営者や決裁者は、現在起きている小さな問題が大きくなる前に何とかしたい、会社を良くしたいと考えてのことですが、現場側からは盛大なため息や不平不満の声が・・・。
なぜでしょうか?
「不安感」を放置するリスク
新しいシステムを導入し、なかなか社内や現場に根付かず困っている、という管理部門の話は珍しいものではありません。システムを提供する会社の営業マンとやり取りをしていた時は、導入1か月後には新システムへの移行がほぼできるとの感覚でいたのに、フタを開ければ何か月たっても移行は完了せず、スタッフたちは旧システムにしがみつき、新システムは使えないという空気感すら漂って、新システムが導入された事実すら無視するものが出てくる始末・・・なんていうことも!?
清掃の現場も同様で、ロボット掃除機という新システムの導入で現場スタッフに動揺が走ることがあります。経営側としてはメリットがあるから導入に踏み切るわけですが、実際に使う現場側には強い不安感が漂い、モチベーションのダウンや使用に拒否感を示されることもあるのです。
・旧システムと並行して使用するためコストが倍増した
・そもそも新システムが使われず費用が無駄になった
・社内の空気がギスギスしてモチベーションが下がった
実際に清掃ロボットを導入した経験のあるお客様からは、以上のようなご相談をいただくことがあります。

その「不安感」の正体は?
結論からいうと、この「不安感」は、具体的なビジョンが見えないことが原因です。
「便利になります」「コストが削減されます」という管理側の簡素な説明では、具体的に自分たちの仕事がどう変わるのかがわかりません。環境の変化で心理的にストレスがかかるうえ、仕事の変化も不透明ときてはモチベーションが下がってしまうこともあるのです。
現場では、日々小さな課題や問題が起きています。現場スタッフの皆様は努力と忍耐でそれらを乗り越えています。そこに新しいシステムが入ると「余裕がないのにタスクだけ増えるのでは」「管理側は思い付きだけで実行しようとしているのでは」と感じてしまうことがあります。清掃ロボットという自分たちと同じ仕事をするものが入る場合、職を失うのではと思われることもあるかもしれません。
導入の目的と、その後のビジョンを共有する
では「不透明から生まれる不安感」はどうしたら解消されるのでしょうか。
人は心理的に、なんだか面倒くさそうだというぼんやりしたものに対してネガティブになりがちです。一方で、ビジョンが明確であり、かつ、便利になる・楽になることに関してはポジティブにとらえます。
管理側はそんなスタッフの心理を理解し、解消できるよう動く必要があります。
1. 現場の問題点を共有し、清掃ロボットの導入でその問題がどう解決されるのかを説明する
2. 清掃ロボットが導入された場合、スタッフの仕事がどのように変化するのかのフローを共有する
3. 清掃ロボットなど新システムの使い方について、寄り添ってレクチャーを行う
というものです。
現場の問題点とは、「コスト高」など管理側が問題視している点ではなく、現場のスタッフが直面しているものです。
・人員不足による個人の仕事の肥大化
・仕上がりのばらつき
・清掃分担での不公平感
などが考えられますが、清掃ロボットの導入よりこれらの問題の解決、あるいは軽減化が可能です。床掃除をロボットにまかせることで、現場スタッフは床清掃以外の業務に集中することができ、フローの簡略化や分担の平均化ができる可能性も高くなるでしょう。それらの認識を現場スタッフと共有し、具体的にフローやシフトに落とし込むことで、現場の不安感が解消されていくのです。
モノの納品だけで終わらない、清掃ロボットの導入

広い施設の清掃は、ただ清掃ロボットを導入しただけでよくなることはありません。現場で活躍するスタッフが、毎日の業務をスムーズにこなすためのツールのひとつとして、現場になじませる必要があるのです。
エムエムインターナショナルでは、清掃ロボットという「モノ」の納品だけに留まらず、清掃ロボットの導入よって清掃現場をどう良くするのかのご提案もいたします。
現場でお仕事をされている方の現状もお伺いし、人とロボットが心地よく協働するため、ロボットの導入だけでなく、清掃全体の伴奏支援も可能です。
ぜひ一度、コンサルティングを含めた清掃ロボットの導入についてご相談ください。
